今回は、クロールの練習方法について書いていきます。
くれぐれも言っておきますが、プールに練習に行くと言って、何も習ったことのない状態で急にクロールを教えることはできません。
足し算ができない状態で掛け算の文章題を解かせているようなものです。
水に顔が付けられる、深くまで潜れる、浮ける、蹴伸びができる。
これらができるようになってからようやくクロールです。
無の状態から泳げるようになるまでには、幼児の場合どんなに早くても3か月はかかるので、気長に練習に付き合ってあげる気持ちが必要ですので、そこだけ覚えておいてください。
以前の記事はこちらを参考にしてください
⓪お家でできる水慣れ方法編
①プールに慣れよう編
②練習への準備編
③蹴伸び練習編
④バタ足練習編
⑤ボビング練習編
⑥息なしクロールの練習編
⑦息継ぎありクロール練習編
練習方法
早速、練習方法を記述していきます。
大まかな流れとしては、プールサイドで手の動きの練習、ビート板を使って練習、ビート板なしで練習といった3段階です。
プールサイドで手の動きを教える
水に入りながらであると、手の動きを教えるのが難しいので、まずはプールサイドで手の動きを教えましょう。
ストリームラインの状態で、ひじを伸ばしたまま太ももに触れ、ひじを伸ばしたまま腕を回していき、元の位置に戻します。
手が帰ってきたら、逆の手を動かし始め、同じ動きをするようにします。
ぶんぶん腕を回すのではなく、初めはゆっくり動かすように意識をさせましょう。
ひじを伸ばし続ける部分が重要です。
ここで注意しなければならないのは、本物のクロールを教えてはいけないということです。
(本来であれば、ひじを伸ばし続けるのは正しいクロールではありません。)
水泳を習ったことがあったり、競技として長くやっていた人ほど初めから正解の泳ぎを教えようとしますが、やめましょう。
理由は単純で、難しすぎるからです。
我々大人は体が十分に発達しており、筋力もそれなりにあるため、ある程度不安定な姿勢でも保つことができます。
ですが、子供の場合は、重心が不安定であり、なおかつ筋力もありません。
そもそも左右非対称な動きをさせるので、導入の際にはなるべくシンプルにわかりやすく、動きやすくしたほうが上達は早いのです。
しっかりとクロールが泳げるようになってきてから、フォームを改善するということで全く問題はないでしょう。
ビート板を使って練習する
続いて、ビート板を使った練習です。
ストリームラインの状態で片手を残しておくのが初めは少し難しいので、ビート板を使用します。
ビート板を持ちながらストリームラインを作ります。
プールサイドでやったのと同じように手を動かします。
おそらく一番難しいのは、太ももを触った後に水面から腕を上げ、元の場所まで戻していく部分です。
しっかりとひじが伸びた状態で、水面から手が出ているかを確認してあげましょう。
彼らにとっては少し難しい動きであるようなので、できたときはしっかりほめてあげましょう。
ビート板なしで練習する
ビート板がありの状態で泳ぐことができたら、次はビート板なしの状態でチャレンジしてみましょう。
ビート板がない場合は、体が沈んで行ってしまうので、キックとの連動が必要です。
キックを同じテンポで打たせながら、それに合わせて手を掻かせるようにしてみます。
初めは難しく感じますが、自分なりにやってごらんといって10回くらい試させると、なんとなくできるようになってきます。
見本を見せてあげるのもいいでしょう。
普通の市民プールであれば、クロールを泳いでいる人がいるでしょうから、それを観察させてみて、イメージをつけてあげるというのも立派な練習の一つです。
まとめ
息なしクロールであっても、習得までには時間がかかります。
1日ですべてを得ようとするのではなく、じっくり少しづつ練習していくというのがコツです。
なぜかわかりませんが、日にちをまたぐと前回できなかったことが急にできるようになっているということが多々あります。
練習がうまくいかないときは、いったん練習から離れてみて、子供の気分が乗ってきたときに再開するというのも一つの手だと思うので、試してみてください。
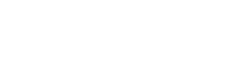



コメント